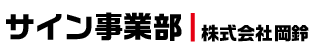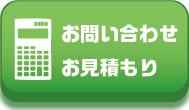銅の錆である緑青は、恐ろしい猛毒と日本でだけ思われていました。しかし昭和37年から3年かけて東大医学部で行われた動物実験の結果、はっきり「緑青が毒だというのは間違いで、他の金属と比較して毒性は大差ない」と学術報告書で結論づけられました。その後国の研究として、国立衛生試験所・国立公衆衛生院・東京大学医学部で追試が続けられ、「緑青は無害に等しい」という判定が下されました(1984年8月6日に厚生省が発表)。もちろん、過激な摂取が有害なのは他の金属や酸素でも同様です。
ちなみに田中正造で有名な足尾銅山の鉱毒は銅の精錬時の煤煙に含まれる公害物質と銅とが結びついた硫化銅や硝酸銅などが水に溶けたもの(緑青は水に溶けない)です。
銅は、鉄や亜鉛と共に人間や動植物に必要な栄養成分です。銅が足りなくなると、貧血を起こしたり(銅欠乏症貧血)発育不良や動脈硬化が促進され老化を早めるとまで言われています。種子・穀物類の他、海の生物、特にノリ・ワカメなどの海藻、エビ・カニ・イカ・タコ・カキなどに含まれています。
さらに銅の殺菌、防藻、防汚作用はチフス菌や大腸菌(そして、その一種であるO-157も)を死滅させる働きがあります。「銅壷の水は腐らない」と昔からの言い伝えや、花瓶の中に銅貨(10円玉)を入れると花持ちが良いのはその効果が現れた例です。銅を繊維にっしたものを使用した抗菌商品も売られています・また、銅製の台所用品はぬめりや悪臭を抑え、プールや下水処理場でも同じ目的で同製品が使用されています。